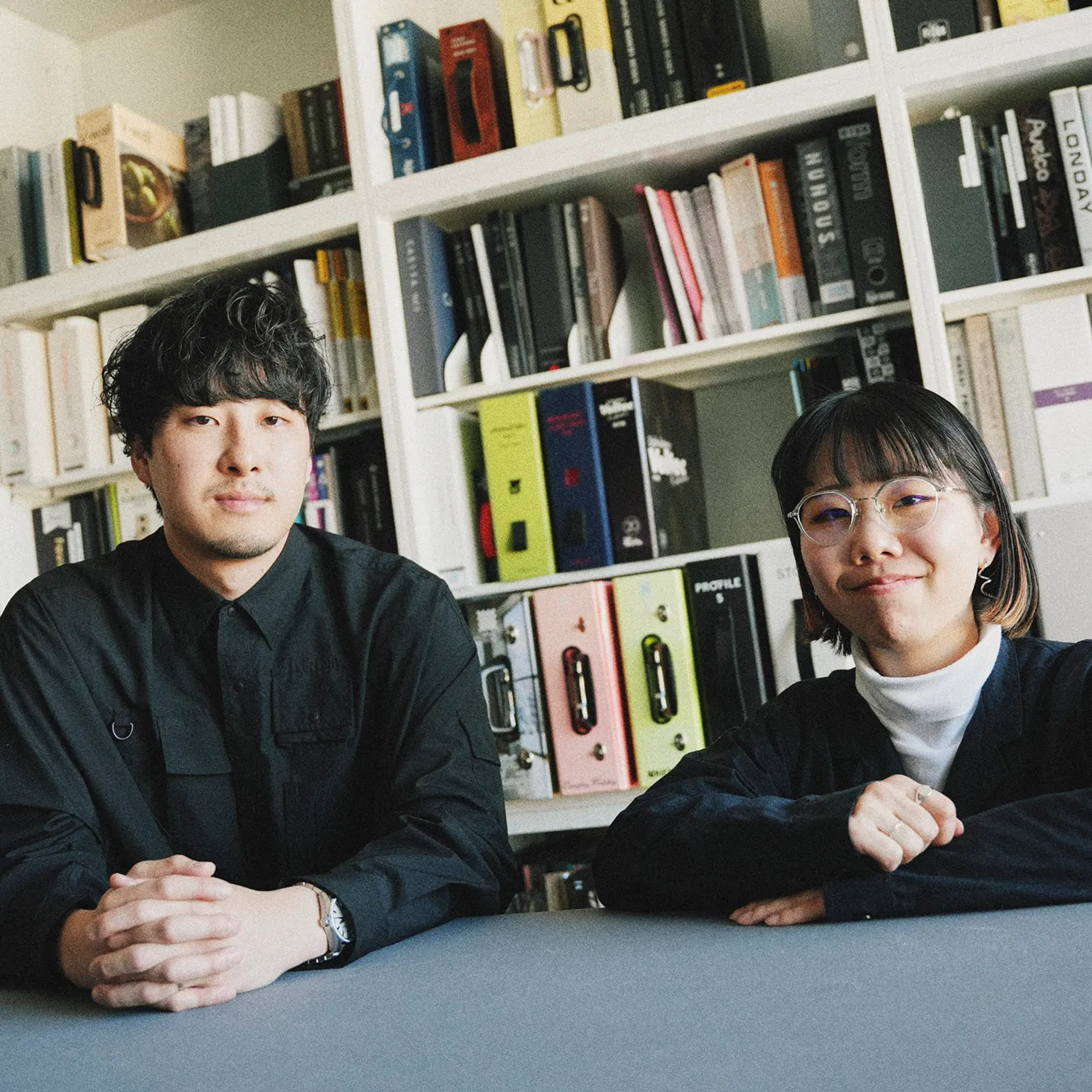CROSS TALK
プランナー職対談
-
熊谷 麻友子
プランナー職2017年入社
-
鈴木 英一郎
プランナー職2017年入社

丹青社のプランナー職とはあらゆる領域で、空間のコンセプトを守り抜く存在
- 鈴木
- 丹青社のプランナーといっても、携わる領域によって役回りや活躍するポイントが全然違ってきますね。
- 熊谷
- コンセプト設計から制作まで一貫して関わりつづけるのはどの領域も同じ。私がメインで担当している展示系の空間では、プランナーと言うとコンセプトや企画設計みたいな川上のフェーズが花形だとイメージされがちだけど、私はコンセプトを落とし込みながら空間をつくり上げていく川下のフェーズのほうが好きですね。だから展示系のプロジェクトはやっていてすごく楽しいです。
- 鈴木
- 私は商業施設系の空間のプロジェクトが多いので、「ものづくり」というより「コンサルティング」に携わっている感覚のほうが強いですね。プロジェクトの川上、つまりクライアントの事業目標達成に向けたプランニング部分が肝になる。どのエリアに出店して、どのようなテナントを施設に誘致すれば売上につながるのか。それを突き詰めるためには「三方良し」の考え方が一番重要で、デベロッパー、商業施設、施設の利用客、全員のメリットを追い求めていかなきゃいけない。そのためにターゲットとなるエリアの顧客属性に基づいてロジックを組み立てながら、売上に貢献する商業施設プランを提案するのが、商業施設系プランナーの最も重要な仕事ですね。
- 熊谷
- 商業施設は一つのプロジェクトで動く金額が大きいから、それだけのお金を投資するに値するプランかどうかシビアに見られますよね。
- 鈴木
- プロジェクトの金額が大きいということは、それだけいろんな人の人生を背負っているということ。一つのレストランを出店するのに、決して少なくない金額が投資されるので、「私たちが責任を持って集客できるようなプランニングをしないと」といつも肝に銘じながら仕事をしています。また周辺に暮らす住人の方々にとっても、商業施設が建つことは日常に大きな変化を生むことでもある。どうしたら皆さんに満足してもらえるのか常に考えつづけています。
- 熊谷
- 竣工後にその空間を使う人のことを考える大切さは、私も実感しています。最近、施設の来場者の方々はもちろん、運営スタッフの皆さんが使いやすい空間を提案できるようになってきました。スタッフさんの動線設計だったり、受付やショップの配置だったり。運営側のパフォーマンスが高まると、来場者の皆さんも楽しめる空間になると思うので、空間を引き渡した先を見据えるように心がけています。

仕事をする上で大切にしていることクライアントやつくり手、みんなで楽しめる仕事に変える
- 熊谷
- 私たちは同期入社で同じ職種ですが、こんな話をする機会はあまりなかった気がします。せっかくなので仕事をする上でのこだわりがあったら聞きたいです!
- 鈴木
- プロジェクトの中で必ず一つ「今までやったことのない新しいこと」に取り組もうと決めていますね。過去の系統とは違うグラフィックデザインを取り入れてみたり、今まで入れたことのないテナントを誘致したり。他社のトレースではなくオリジナルで勝負するのが、丹青社のクリエイターの存在意義だと思うので、社名に恥じないように常に新しいことに挑む姿勢を大切にしています。……と熱いことを言いつつ、新しいことを提案してクライアントに共感してもらったほうが、プロジェクトが楽しく進められるからという理由もあるんですけどね(笑)。
- 熊谷
- 結局、みんなで楽しく仕事をすることが一番なんですよね。展示系の空間はほとんどが長期プロジェクトになるので、クライアントにとって一度あるかないかの出来事になることが多い。だからこそ、一生に一度の展示空間づくりを楽しんでほしい。特に打ち合わせはクライアントに楽しんで空間づくりに参加してもらうために、「ライブ感」を大事にしています。最近だとグラフィックデザインを投影したり、模型を持ち込んだりして、クライアントの要望をその場で反映していきながらアウトプットを詰めていったり。一緒に空間をつくり上げていったことで、クライアントとの距離もすごく縮まった気がしますね。
- 鈴木
- 「ライブ感」いいですね。お互いに納得いくものがつくれるような場をセッティングするのもプランナーの大事な役割ですよね。クライアントとの関係づくりもそうですが、多種多様なブレーンさんとチームを組みながら自分の好きなようにプロジェクトを進めていけるのも、プランナー職の魅力ですね。
- 熊谷
- 丹青社としてもいろんな領域のブレーンとのコラボレーションを推奨していて、個人的にはこれまでになかった視点を共有してもらえるので、協力会社さんに積極的にオファーをしています。例えば、ある展示会のプロジェクトでサウンドデザイナーの方に協力依頼をしたことがあって。一般的に協力会社さんには制作段階で参画してもらうことが多いんですが、そのプロジェクトでは音づくりが重要になると考えて、コンセプト設計から一緒に考えてもらうことにしました。まだコンセプトの段階なのに、音で表現した時のアイデアをたくさんもらえて、今までとは違うコンセプトの捉え方ができて新鮮でした。
- 鈴木
- 丹青社として空間づくりにとどまらず新しい領域へと可能性を広げようとしている中で、いろんな領域のプロフェッショナルとの協働は、ますます鍵になっていきそうですよね。そのプロフェッショナルたちとのつながりの中心にいるのが私たちプランナーであり、協働の中でコンセプトを貫きながらゴールに向かってチームを推進できる存在でありたいですね。

丹青社のプランナー職に求められる考え方チームの中心で「ベストな空間」を追求しつづける
- 熊谷
- 最後に、この記事を読んでいる皆さんに向けて「丹青社のプランナー職に求められる考え方」について伝えられたらと思いますが、鈴木さんからお願いします!
- 鈴木
- これまで「プランナーとはコンセプトをブラさずに守り抜く仕事」という風に話してきましたが、軸を持ちながらもいろんな人の意見を柔軟に受け入れる姿勢が、チームで仕事をする上で求められることだと思っていて。この仕事をやっていると、クライアントとつくり手で意見が食い違ったり、納期ギリギリで修正が発生したり、自分の意見がそのまま通らない場面が山ほど出てくるんですよね。そんな中でもクオリティの高いものを納品するために、みんなの意見の落とし所を探っていかなければならない。コンセプトをブラさないという意思を持ちながらも、それだけに縛られず、チームの進むべき方向を柔軟に決断していくことが大事なんだなって、プロジェクトを経験するごとに実感しています。
- 熊谷
- コンセプト設計から完成まで、楽しいことももちろんありますが、思い通りにいかないことも多い。そこでめげずに突破法を模索しつづける姿勢が、プランナーに必要な素養だと思います。自分がいいと思うものとクライアントがいいと思うものがぶつかった時、どうすれば双方とも納得のいく空間になるのか、諦めずに次から次へと提案する。そんなめげない気持ちがあれば、スキルや審美眼はいくらでも磨かれていくと思います。それでもどうしても心が折れそうになったら、チームの仲間に相談して励ましあったり、空間を楽しんでくれる人たちの顔を思い浮かべたりしています。そうすることで「絶対いいものをつくってやる!」っていう気持ちが沸いて、問題を乗り越えるモチベーションになりますね。
- 鈴木
- プロジェクトを経験するごとに着実にプランナーとしてできることは増えていくし、できることが増えるとプロジェクトの幅も、丹青社の領域も広がっていく。そんな連鎖をこれからも生み出していけたらいいですね。