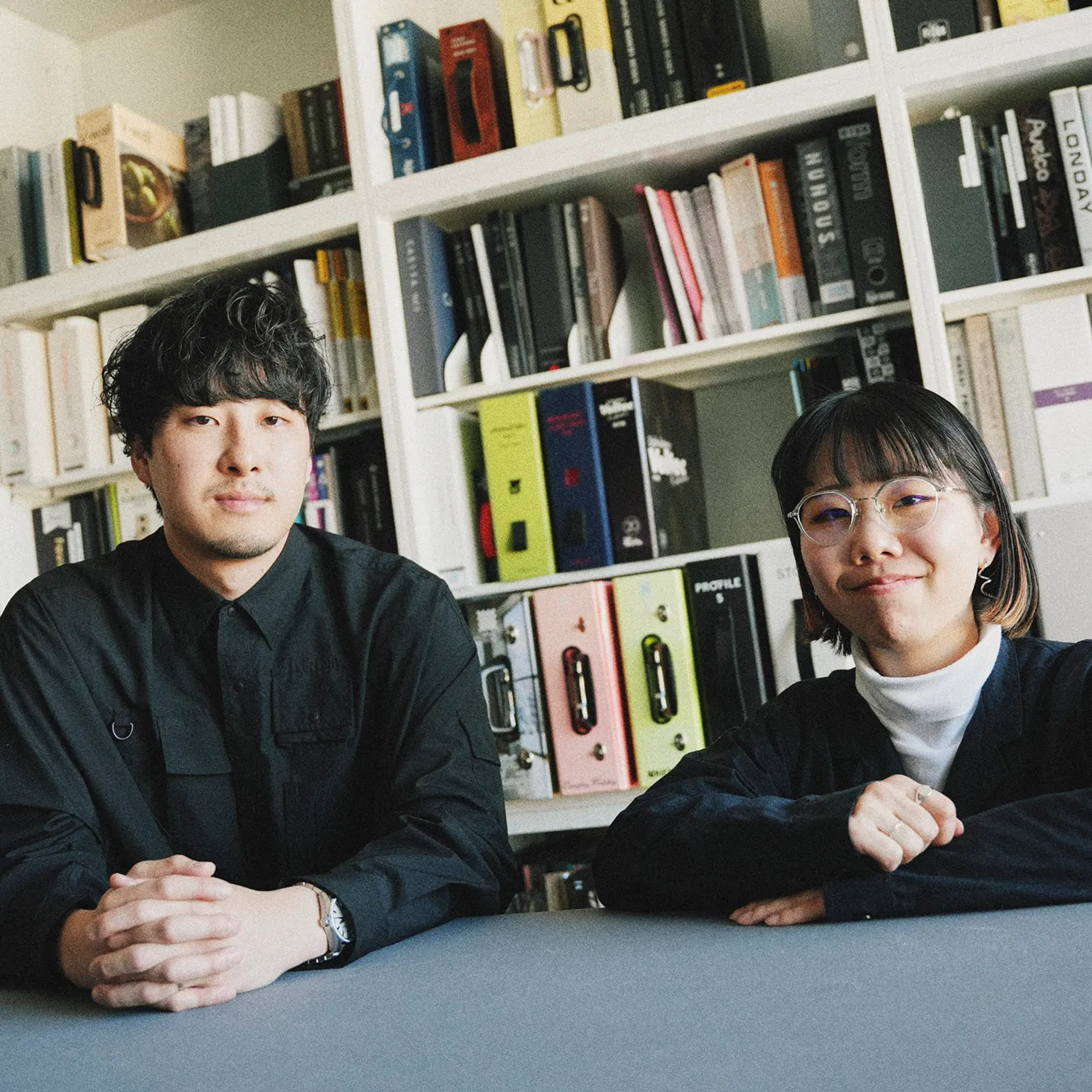CROSS TALK
演出・体験クリエイション職対談
-
髙橋 晴
演出・体験クリエイション職2023年入社
-
沢木 和樹
演出・体験クリエイション職2016年入社

丹青社の演出・体験クリエイション職とは空間の体験価値を最大化する演出技術を、トータルで請け負う
- 沢木
- まずはじめに自己紹介をすると、私たち二人は演出・体験クリエイション職としてCMIセンターという部門で働いています。CMIセンターの使命は、映像や照明、音響、模型、センシング……などあらゆるテクノロジーを駆使しながら、空間体験の価値を最大化すること。当センターには私たちのような演出技術に特化したメンバーが多く在籍しており、空間を構成する床・壁・天井以外の演出領域のデザインをトータルで担当しています。
- 髙橋
- 空間の感動体験につながれば、アナログやデジタルにこだわらず何でもチャレンジできる自由な職場ですよね。
- 沢木
- そうですね。この仕事をやっていると、空間づくりにおいて演出技術に対する期待度は年々高まっていると感じます。ちょっと前までは、床・壁・天井がデザインの中心で、映像や照明は補助的な立ち位置でしたけど、今は「映像や照明を含めたデジタルテクノロジーを使った演出をやりたい!」というクライアントがすごく増えましたね。デジタルコンテンツ主体の博物館が増えたり、商業施設にプロジェクションマッピングを取り入れたり。
- 髙橋
- 技術がどんどん進歩して、CMIセンターに相談が来る案件も年々多様化してますね。そのおかげで、「新しい知識やトレンドを掴みにいかなきゃ!」と日々前のめりに仕事ができています。自分の中に引き出しがないと、クライアントの予想を超える提案はできないので。引き出しを増やすために、海外の事例を調べたり、他社の事例を見に展示会やイベントに足を運ぶようにしています。体験している時はなるべく何も考えずに空間を感じようと心がけているのですが、気が付くとついつい「この映像はどのプロジェクターから投影されているんだろう?」って演出技術の部分に意識がいっちゃうんですよね(笑)。
- 沢木
- それ、すごくわかります。私も遊園地でライド系のアトラクションに乗っている時、頭の中でシステムの設計図を考えちゃっています(笑)。
- 髙橋
- もう職業病ですよね。だけど、そういう視点を通して得た気づきが自分のプロジェクトにつながることが多いので、これからもいろんな場所を訪れようと思います。

仕事をする上で大切にしていることこだわり抜く力と自由な発想力が、空間のクオリティを上げる
- 髙橋
- せっかくの機会なので、沢木さんに仕事をする上で大切にしていることを聞きたいです!
- 沢木
- 自分らしさをきちんと持つことですかね。私たち演出・体験クリエイション職は設計やプランナーから声をかけられて案件に参加するから、「この案件は沢木に頼もう」と思ってもらわないといけない。そのために「沢木といえば」を明確にする必要があると思っていて。私の場合は、クライアントや制作メンバーが求めていることを的確に汲み取って言語化する力が自分の強みだと思っています。特に大型案件になるといろんな職人さんと協働することも多いから、クライアントの想いを齟齬なく現場に伝えるスキルが重要になってくるんですよね。案件の規模に関わらず、自分の強みは言語化力だという意識を持って、チーム内のコミュニケーションに気を配りながら仕事をしています。
- 髙橋
- クライアントの想いを制作側に伝えるのもそうですし、まだ漠然としているクライアントの要望を具体的な施策に落とし込むのにも言語化力は生かせそうですね。
- 沢木
- そうですね。クライアントによってはデジタルでどんなことができるのかわからないケースも多いので、こちらからやりたいことを引き出して、言語化してあげることが大事になってきますね。髙橋さんが仕事をする上で大事にしていることは何ですか?
- 髙橋
- 私は「細かいところまできちんとこだわり抜くこと」ですね。「このくらいで大丈夫か」とは決して思わないように意識しています。企業ショールームの案件で、円形スクリーンのシアタールームを制作することになった時、複数枚のスクリーンを円形につなぎ合わせて映像を映していたんですけど、スクリーン同士のつなぎ目が若干甘かったんです。本当にちょっとだけだったので迷ったのですが、「このままじゃダメだ」と思いとどまって職人さんにつなぎ直していただきました。どんなに凝った映像をつくっても、投影するスクリーンのクオリティが低いと、映像体験そのもののクオリティも下がってしまう。クライアントの想いを純度高く届けたい一心で、細部までとことん詰めていきました。
- 沢木
- 「自分がつくりました!」って自信を持って言うためにも、細かなこだわりは大事ですよね。特にデジタル系のコンテンツだと、スクリーンとか投影機器とか、映像や照明を見せるにあたって目立たせたくない機材が多いので、空間体験を損なわないように細かくこだわりながら制作する必要があるから大変ですよね。
- 髙橋
- そうですね。演出が複雑になるほど使用する機材も増えるので、そのたびに悩みますよね。沢木さんが演出のアイデアを考える時に意識していることはありますか?
- 沢木
- 固定観念からはみ出そうとは、日頃から意識しています。例えば、映像演出系の体験施設の場合、没入感を演出するために基本的に機材は真っ黒にするんですけど、機材を黒塗りにしたり貼ったりすると、保証が効かなくなることがあるんですよね。「機材を黒くできて、かつ電波を遮断しないものって何だろう?」って考えた末に、タイツだとひらめいたんです。
- 髙橋
- 履くタイツですか?
- 沢木
- はい。機能として今回の目的にピッタリだったから採用することになって。「タイツ=履くもの」という固定観念にとらわれないで、機能や目的をクリアしていれば、どんな手法を用いても良いと思って自由に考えられると、面白いアイデアにつながるんじゃないかと思っています。そういう意味で言うと、訪れる人の体験価値を最大化するためなら、デジタルに固執する必要もないと思っているんです。丹青社はデジタルを使った演出も多いけど、訪れる人が喜ぶならアナログ的なアプローチもするべき。目的を捉えながら、自由に考えることが大事なんだと思います。
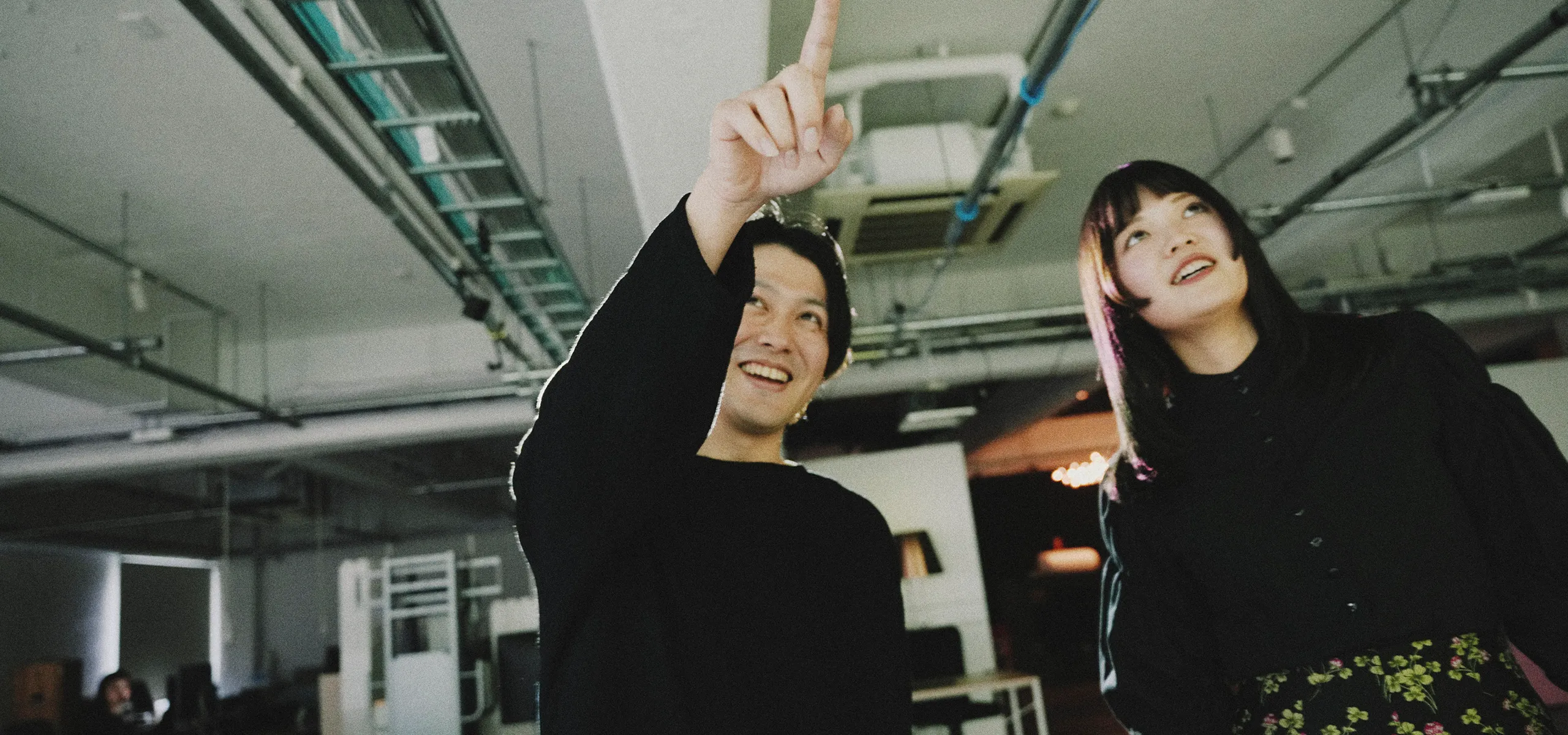
今後の展望新たな演出技術で、誰も体験したことのない空間をつくりたい
- 沢木
- 最後に「今後の展望」について話せればと思いますが、髙橋さんはいかがでしょうか?
- 髙橋
- 見た人がどうやっているのか仕掛けがわからないデジタル演出に挑戦してみたいです。CMIセンターはデジタル系の案件が多い部門ですが、空間に携わる者としてアナログの良さは大事にしたいと思っています。つまり、その空間にいるからこそ味わえる驚きを多くの人に体感してほしいです。デジタル技術のレベルが上がれば上がるほど、見た人は仕組みがわからなくなる。それはもはや魔法だと思っていて。例えばあるテーマパークのアトラクションで、立体が忽然と消える演出があるのですが、何回見てもどういう仕掛けなのかがわからないんですよ!周りに機材がないか、くまなく目を凝らしても何も見つからない。つくり手の徹底したこだわりに魔法が宿るんだなと感激しましたね。同じつくり手として大きなモチベーションになっています。
- 沢木
- そういうレベルの高い技術を見ると燃えますよね。個人的には、まだ見ぬ技術にチャレンジして、未来の常識になるような空間をつくりたいです。プロジェクションマッピングも今やいろんな商業施設が取り入れるようになって、スタンダードな演出になりました。今まさにホログラムや超音波、触覚テクノロジーみたいな新規性が高いとされている技術の黎明期で、新技術を取り入れながら空間演出の世界をもっと盛り上げていきたいですし、CMIセンターならそれができると信じています。
- 髙橋
- 新しい技術を取り入れて、その先にどんな空間ができあがるのか、ワクワクしますね!私も誰も見たことのないような驚きのある空間づくりを目指して、いろんな領域に挑戦したいと思います!