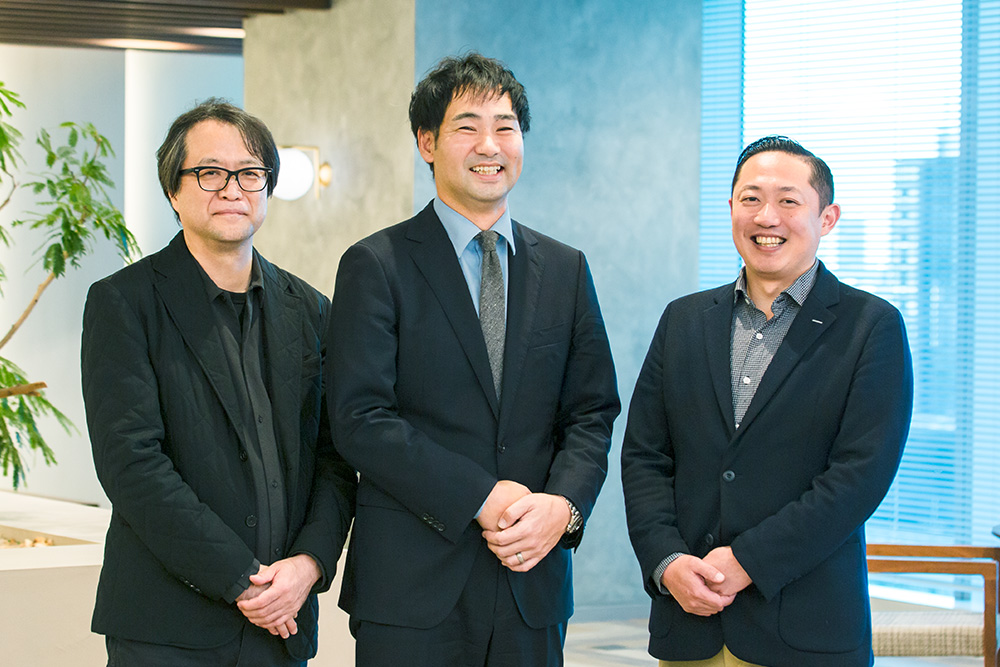宮本 充
(左)株式会社丹青社
文化・交流空間事業部 プロデュース事業統括部 運営プロデュース部 1課 課長
富山県出身。2016年にキャリア採用で丹青社へ入社。以降、運営プロデュース部にて現場と並走して担当施設事業の推進管理を中心にさまざまな公共施設の運営業務に携わってきた。同部では鳥取県立美術館を含む公共施設の運営に携わっており、宮本本人も複数の施設を担当している。
砂川 亜里沙
(右)株式会社丹青社
文化・交流空間事業部 プロデュース事業統括部 事業開発部 官民開発推進課 プランナー
神奈川県出身。2019年にキャリア採用で丹青社へ入社。事業開発部で施設運営に関する提案や営業活動、開館までの企画推進や計画づくりに横断的に携わる。鳥取県立美術館においては、主に開館準備期のプロジェクト推進を担当。
稲葉 直也
(中)株式会社丹青社
文化・交流空間事業部 プロデュース事業統括部 運営プロデュース部 1課
愛知県出身。2021年に丹青社へ新卒入社して以来、一貫して鳥取県立美術館のプロジェクトに参画。入社後4年間の開館準備期は砂川と同じく事業開発部で、2025年度からは宮本の所属する運営プロデュース部にて現在もプロジェクトの中枢で運営事業にあたっている。
初めてづくしの美術館づくりプロジェクト
宮本
鳥取県立美術館ができるまで、鳥取県は国内でも数少ない「県立美術館のない都道府県」でした。加えて、本プロジェクトは新設の美術館として全国初の施設整備から運営維持管理一体的なPFI事業であり、かなり注目度が高かったと思います。
稲葉
PFIとは、美術館や博物館など公共施設の設計建設や改修、運営などを、国や地方自治体から民間企業に発注して行う公共事業手法のことです。公共としては、資金調達などコスト面の負担減や質の高い公共サービスの提供を叶えられ、私たちのような民間にとっても事業創出の機会が生まれるといったメリットがあります。
宮本
これまでも、すでに開業している公共施設の運営維持管理業務を指定管理者や業務委託などで民間に発注するケースは多くありました。しかし鳥取県立美術館の場合は、新たに美術館を建てる設計建設・運営維持管理と包括的にPFIを採用している点で、全国初のケースなのです。丹青社としても、これまで20年近く施設運営や事業プロデュースに携わってきましたが(現在全国20施設)、開館準備期間が5年と長期にわたることや、開館前から多くの事業パートナーや地域と密に連携を図り大規模な機運醸成事業を展開したことなど、挑戦の多いプロジェクトとなっています。
砂川
丹青社としては、設計事務所や建設企業、運営、清掃・警備会社など各領域専門10社からなるコンソーシアムに参画し、展示収蔵環境づくりのほか、ポップカルチャー企画展や広報・ブランディング方針、ショップ・カフェなども含めた提案をさせていただきました。優先交渉権者として選定されたときは嬉しかったですが、そこから開館に向けた準備はとにかくいろいろありましたね(笑)。
宮本
そうですね。まず事業開始の時期がコロナ禍と重なり、事業パートナーとなる県やコンソーシアム各社とのコミュニケーションがオンラインのため、関係構築や共通イメージを持つためには一段と工夫が必要でした。現地で運営に携わる常駐スタッフの採用では、ありがたいことに全国から応募をいただき、リモートと対面を織り交ぜて進めました。毎回、施設運営に向けた組織づくりには特に力を入れて取り組んでいます。
砂川
結果的に、すごく熱意のあるメンバーが集まり、出会いに恵まれたなと思います。開館後も本社から一方的に指示をするのではなく、計画時に余白を設け、現地で地域の方々と直接接しているメンバーが何をしたいのか、地域の声や社会の動きも踏まえて主体的に考え、具体化することを大切にしています。本社も一緒に知恵を絞り、会社のリソースも活用しながら実現に向け支援する。地域と丁寧に対話し、企画推進に活かし、それを高い熱量で実践し続けている現地運営メンバーの皆さんには本当に頭が上がりません。

鳥取県立美術館を象徴するコンセプト「OPENNESS!」
砂川
本プロジェクトにおいて特にこだわったのが、「OPENNESS!」というコンセプトの体現です。この言葉は、当時の鳥取県博学芸チームと半年ほど意見を出し合いつくり上げたもの。作品はもちろん、情報も仕組みもできるだけオープンに、地域に開かれた美術館にしていこうという意思を込めています。鳥取県の美術作品や風土の特長は何か、学芸チームが大切にしていることは何か、設計や運営の特長は何かなど、“鳥取県立美術館として”の個性を端的に表すことを関係者一丸となって話したことで、ビジョンの輪郭がはっきりしてきました。その後の計画やイベント企画で悩ましいことがあっても、振り返れば「OPENNESS!」の視点が常に判断軸にあったように思います。
稲葉
大きく開放的な雰囲気のある窓やひろま、誰でも無料で立ち寄れるオープンスペースなど、美術館そのものが「OPENNESS!」を体現するつくりになっていると思います。加えて、さまざまな仕組みやプロセスにおいても「OPENNESS!」を意識していて。その象徴とも言えるのがロゴ・シンボルマークの公募です。小学生からプロのデザイナーまで広く誰でも応募できるような形式をとり、最終的には1,726名もの方から応募をいただきました。さらに、発表会では採用されなかった案も含めすべて展示したことも、「OPENNESS!」のコンセプトに基づいています。
宮本
私としても「OPENNESS!」のコンセプトはブレないようにプロジェクトを推進してきました。何かイベントをやる際には、必ず鳥取県の東部・西部・中部3地域で説明会を開催し、県全体を巻き込むよう心がけていましたね。その点ではショップやカフェの準備も県内を奔走しました。
稲葉
ミュージアムショップは丹青社が直接運営を行い、カフェは地元のパートナーの企業と連携して運営しています。ゼロからの立ち上げだったので、コンセプトづくりからオリジナルグッズの開発、商品の仕入れ、店舗づくりまでやることがたくさん……。立ち止まる時間はなかったので、考えながら走り抜けました(笑)。
最初から「アートとの出会いの場」や「鳥取県の自然・文化を反映したものづくりを伝える場」というイメージはありましたが、それを具体化するためには地元の企業やつくり手の方の協力が不可欠です。最初はまったく繋がりがなかったので、事業者向けの説明会を開いたり、店舗や工房を訪問してお話を聞いたり、関係性を少しずつ築いていきました。
幸いなことに、地域に根差したデザイナーや民工芸のセレクトショップを運営する方、障がい者アートの支援をされている方などのキーパーソンと出会い、徐々に店の骨格が固まっていきました。足しげく鳥取へ通い、因州和紙の工房や民藝の窯元などを訪ねてオリジナル商品の打合せをした日々は、個人的にも印象に残っています。鳥取の豊かさや県民の皆さんの温かさに触れると同時に、県立美術館への期待の大きさも感じ、やりがいのある仕事でした。
結果的に、美術館のシンボルマークやコレクションをモチーフにしたオリジナル商品、鳥取県の民工芸、障がい者アート関連グッズなどを扱う、鳥取県立美術館ならではのショップを形にできたと考えています。開館後、倉吉の街でミュージアムショップの手提げ袋を持って歩かれている方を見かけると、心の中で感謝と喜びを感じています(笑)。自分ひとり、丹青社単独ではできなかったことが、「みんなでつくる」中で実現していったことは、美術館のコンセプトにも繋がりとてもよかったと思います。
砂川
県・コンソーシアム全体に「みんなでつくる」という意識があったのが、すごくよかったですよね。設計建設企業が中心となり、運営企業も一緒になって建設現場見学会を開催したこともありました。上棟イベントで美術館から餅まきしたり、建設現場の中をツアー形式で案内したり、開館後をイメージした体験をちりばめたり。パースでは伝わりきらない美術館のスケール感や、何もなかったところに多くの方が集まる様子は印象的でした。プレスの方にも多く取り上げていただき、回を追うごとに「また来たよ」「また来るね」と大人も子どもたちも目を輝かせて、美術館をみんなで楽しみにしていく気持ちが育っていくのを目の当たりにできて。鳥取県立美術館を知ってくださる方が増えている実感がわき、私たちもだいぶ励まされました。
宮本
あとはやっぱり、現地運営メンバーの活躍が大きいですよね。現地メンバーが中心となって、県・コンソーシアム関係者、そして鳥取県民の皆さんと数えきれないほどのコミュニケーションをとりながら、文字通り道なき道をかけぬけました。「よい美術館をつくりたい」という強い想い、熱意がダイレクトにさまざまな人に伝わったからこそ、プロジェクトがぐんと前に進んでいったんだなと振り返っています。ミュージアムショップの店長は、お客さま全員顔見知りなんじゃないかと思うほど地元の知り合いが多くて。まさに「OPENNESS!」を体現してくれていると思います。移住してまで推進してくれるメンバーに出会えたこと、熱意あるメンバーが集まったこと、現地と本社、協業パートナーと当社でよいチームができ、相乗効果で力を発揮できたことが良いプロジェクトにつながっていると感じています。

施設の価値を高める取り組みに、丹青社として挑戦していく。
宮本
丹青社の本業では、施設の空間づくりを行い、事業主に引き渡すまでを支援させていただくことが多いです。しかし私たちが携わる施設運営事業では、その後の施設の価値を高めていくことに、中長期的に携わっていくことになります。大変なことも多いですが、鳥取県立美術館のような事例をもっと増やしていけるよう、継続的に取り組んでいきたいです。
稲葉
鳥取県立美術館に関していえば、年に1度開催する「ポップカルチャー企画展」の企画・実施を15年間継続的に行なっていきます。現地運営メンバーとも連携しながら、皆さまに楽しんでいただける企画展にしていきたいです。
入社し鳥取県立美術館に携わって5年、鳥取はもはや第二の故郷だと思ってます(笑)。それくらい思い入れの強い事業に携われた経験を踏まえて、文化資源を活かした地域活性化にこれからも取り組んでいきたいです。
砂川
鳥取県立美術館のようなPFIなど包括的に関われる実績を増やしていき、これまでなかったようなお困り事にも丹青社として一気通貫でお応えできるようになっていけるといいなと思います。そのためにも、これまでのやり方に固執することなく、柔軟にチャレンジしていきたいですね。

丹青社開発のオリジナルグッズ例(ロゴ・シンボルマークやコレクションモチーフの館オリジナルグッズ、県内事業者と共同開発したマグカップ)
| 施設情報 |

鳥取県立美術館
所在地:鳥取県倉吉市駄経寺町2-3-12 |
|---|
関連ページ